分党・解党・分派の関係~政党の離合集散で登場する用語

政党がくっついたり離れたりする時によく耳にする「分党」「解党」「分派」という用語。
確かに総務省のホームページで調べると、用語の違いが解説されています。
ただし、「分党」「解党」「分派」は法律の条文にある言葉ではなく、各政党が党規約や党則などで独自に定める手続き上の言葉でもありません。
本記事は、政党の離合集散のたびに登場する上記3ワード(分党、解党、分派)を正しく理解したい方向けに解説しました。
【目次】※項目を選ぶと移動します。
分党とは?
政党が解散(=解党)し、2つ以上の新しい政党が設立される動きを「分党」という言葉で表現しています。
「分党」という言葉が使われる際は、存続政党が解散される、いわゆる「解党」が必ず起こる事が前提になります。
根拠となる法令が政党助成法という法律です。
「分党」は、この政党助成法で規定される「政党の分割」と同じ意味です。
同法の規定に基づき、国から毎年、政党交付金(=政党助成金=国の税金=政治資金の一種)が所属議員数に応じて比例配分されます(参照先⇒「政党の合併・分割の類型と政党交付金の計算」へ)。
もし、分党をすぐに進めたくない場合は、政党の解散に合意しない姿勢を貫けば済みます。
解党とは?
解党は、政党の解散そのものです。
政党の解散後は、新しい党を設立して分党(政党の分割)や合併(合流)する方法もあるし、全員が無所属になる道もあります。
だから、解党は、分党や合併の前段階の状態を指します。
解党の手続
政党の解散や、目的の変更等で政治団体でなくなったり、あるいは政党交付金の交付対象としての要件を満たさなくなった場合、政党の代表は、原則その日の翌日から15日以内に、総務大臣に届け出る必要があります。
具体的には、政党解散届を党本部がある選挙管理委員会に提出し、総務省から受理されると解散になります。
分派とは?
分党と似た表現に「分派」があります。
混同しないために説明すると、分派は「分党」(「政党の分割」)の一種ではなく、別物です。
政党は存続した(=解党しない)まま、一部の所属国会議員が脱退(離党)して新しい政党を設立する動きを「分派」と言います。
この場合、新党に対しては政党交付金(=政党助成金=政治資金の一種)は配分されず、存続政党が丸々受け取ります。
したがって、所属政党を脱退(離党)する議員には、脱退する年に政党交付金(政治資金)が入らないデメリットが生じます。
分派に伴う政党交付金の配分は政党助成法が根拠となりますが、同法に「分派」に関する定義や規定は存在しません。
つまり、「分派」は、同法が規定する政党の解散(解党)、さらに解散後に起こりうる合併や分割と直接には関係するものでなく、ただ単に政党助成法の解釈に基づくものです。
分党(分割)や合併で設立できる新党の要件
分党や合併における政党の要件も、政党助成法で定めれられています。
以下、条件Aか条件Bのどちらかを満たせば、政党(国政政党)として認められます。
- A.所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上を有する政治団体
- B.衆議院議員か参議院議員を有するもので、合併または分割の日の直近の総選挙(衆議院)もしくは直近か前々回の参院選通常選挙(参議院)で当選した議員の得票総数が有効投票総数の2%以上である政治団体
すなわち、分党を実現するという事は、政党を解散(=解党)後に条件AかBを満たす政党を設立する事を意味します。
条件Bは、最低でも国会議員1人が政党に所属し、かつ過去の選挙で議員が得た票の総数も計算する必要があります。
新党に関する報道ニュースを見ると、議員5人以上が参加するか否かが焦点として、よく取りざたされます。
これは、条件Bは計算が面倒なので、まずは条件Aを満たすか否かが注目されるためです。
政党の合併・分割の類型と政党交付金の計算
以下に、政党の合併と分割の各パターンと政党交付金の配分を図解しました。
政党の合併・分割等が行われた場合の政党交付金
| 政党の異動 | その年(総選挙又は通常選挙がない場合)の政党交付金 | 次回以降算定される政党交付金の額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 議員数割 | 得票数割 | |||
| 新設合併 |  |
A党、B党の政党交付金を合算した額 | 基準日現在の議員数により算定 | A党、B党の得票数を合算した得票数により算定 |
| 存続合併 |  |
A党、B党の政党交付金を合算した額 | 基準日現在の議員数により算定 | A党、B党の得票数を合算した得票数により算定 |
| 分割 |  |
A党の政党交付金を単純に議員数に応じて配分した額 | それぞれ基準日現在の議員数により算定 | A党の得票数を、算定の基礎となる選挙においてA党に所属する候補者であった議員数に応じて配分した得票数により算定 |
B党分=A党分残額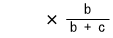 C党分=A党分残額 b、cはB党又はC党に設立時に所属する国会議員のうちA党解散時にA党に所属していた人数 |
B党分の得票数=A党得票数 C党分の得票数=A党得票数 b’、c’はb、cのうち、A党所属候補として選出された者の人数 |
|||
| 分派 |  |
A党…当初決定どおりの額 B党…なし |
それぞれ基準日現在の議員数により算定 | A党…A党の得票数により算定 B党…なし |
日本における分党・分派の実例
分党も分派も党内分裂である事に変わりはありませんが、「分党」=協議離婚、「分派」=泥沼離婚の様相を呈する場合が多いです。
以下は、平成以降に起きた主な実例の一部。
<分党の実例>
| 1997年 | 12月27日に両院議員総会を開いて新進党の分党と新党の結成を宣言。これによって新進党は消滅し6党に分裂。 12月31日に政党助成法に基づく分党手続、新進党解散。 |
| 2014年 | 6月22日に日本維新の会が分党を決定し、7月31日に解党。当時同党の共同代表を務めた石原慎太郎支持派のグループによって8月1日、次世代の党(2015年12月21日、日本のこころを大切にする党に党名変更)を結党。 |
| 2018年 | 5月7日に国民党と希望の党(新)への分党手続きを行い、希望の党(旧)を解党。国民党は同日付で民進党と合併し、国民民主党となる。 |
<分派の実例>
| 2000年 | 自自公連立政権をめぐり、3月に連立離脱派(自由党の小沢一郎党首グループ)に対し、連立継続派が新党(保守党)を結成。保守党は過半数の参加を基に自由党に分党要求。分党を拒否されたため、離党による新党結成の手続をとり、政党助成金は2000年6月の総選挙後まで交付されず。 |
| 2014年 | 10月14日、維新の党内で執行部(結いの党=みんなの党系中心の残留組)と橋下徹大阪市長を中心とする新党参加組(おおさか維新の会)が、分党協議で決裂。 その後、新党参加組が執行部から大量に除籍処分を受ける。11月2日、新党参加組により、おおさか維新の会(後身:日本維新の会)が結成される。 |
まとめ
「分党」「解党」「分派」は、各政党が独自に規定したルールに沿って行われる行為ではありません。
また、法律の条文で使われる言葉でもありませんが、政党助成法の中で規定される政党の合併、解散、分割と密接です。
国政政党が分裂する場合は、「分党」か「分派」のいずれかの選択肢を迫られます。
「分党」と「分派」の特に大きな違いは、分裂した双方に政党交付金が分配されるか否かにあります。
分党も分派も政党のあり方を左右する意味で、本来は有権者に関係する大事なテーマです。
しかし、歴史を振り返ると残念ながら、有権者は蚊帳の外で、当事者間の醜い利害対立に終始する場面ばかり見せつけられます。
結局、党の抗争と分裂には、人間の感情対立も増大して有権者そっちのけの非生産的な時間一色になりやすいので、当事者はできる限り、短期間で終わらせる姿勢を意識すべきだと強調しておきます。
参考URL
政党助成法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406AC0000000005
政党助成法のあらまし
https://www.soumu.go.jp/main_content/000161030.pdf
総務省|VIII 政党の解散、合併、分割等
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou08.html
永田町に再編の嵐 政党が分割・合併するって? :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO75366460X00C14A8000098/


